このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?
結論から言えば、スキルアップしたい人や転職・キャリアアップを目指す人にとって、資格は大きな武器になります。
そして重要なのは、工場勤務で「実務に直結する資格を選ぶこと」です。
この記事では、実際の現場で役立ち、転職にも有利なおすすめ資格を8選を紹介します。
後悔しない資格取得になるよう、ぜひ参考にしてください。
工場勤務で資格を取得するメリットとは?
主なメリットとしては、以下の通りです。それぞれ詳しく解説していきます。
- スキルアップできる
- 評価や昇給につながる
- 転職がしやすくなる
スキルアップできる
仕事に必要な知識や技術を体系的に学べるため、実務力が大きく向上します。
また、機械操作や安全管理などを正しく理解することで、作業の正確さや効率もアップします。
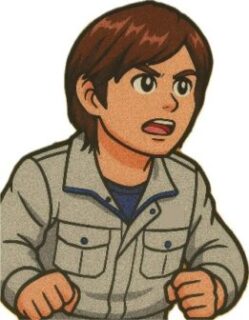
仕事の幅や見解が広がり、広い視野を持つことができるようになるでしょう!
評価や昇給につながる
工場で資格を取得すると、専門知識や技術を持つ人材として評価されやすくなります。
資格を持つことで作業の信頼性が高まり、責任ある仕事を任される機会が増えるでしょう。
会社によっては、昇給や資格手当などの待遇面で優遇されるケースも多く存在します。
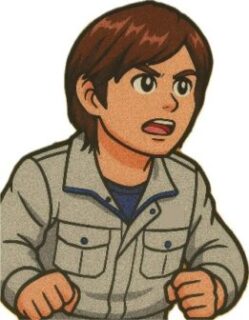
高い評価を受けたり、昇給できたりすれば、自分の自信やモチベーションアップにもつながるでしょう!
転職がしやすくなる
資格を取得すると、自分の知識や技術を証明できるため、転職の際に大きな強みになります。
採用担当者は「この人は即戦力として働ける」と判断しやすくなり、未経験の業界や職種でも採用されやすくなります。
特に工場では、フォークリフトや危険物取扱者の資格があると、採用される可能性が高まります。
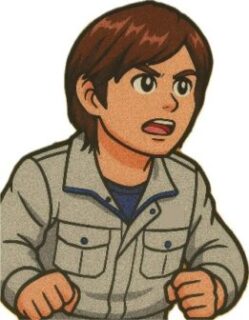
資格は自分の能力を示す“信用の証”となり、より有利に転職活動を進められるのです。
工場全般で使えるおすすめの資格8選
工場勤務において、実際の現場で役立ち、転職にも有利なおすすめ資格を8選を紹介します。
それでは、それぞれ見ていきましょう。
- フォークリフト運転技能者
- 玉掛け技能講習
- クレーン運転士
- QC検定(品質管理検定)
- 危険物取扱者(乙種第4類)
- 第二種電気工事士
- 機械保全技能士
- 衛生管理者
フォークリフト運転技能者
フォークリフトの資格は、「重量のある荷物の運搬作業」を行う際に必須とされる国家資格です。
工場勤務では、原材料や完成品を搬入・出荷する工程が多く、資格を持つことで担当できる作業の幅がグッと広がります。
とても便利な機械ですが、操作には一定の危険を伴うため、資格を持つ人だけが運転できます。
この資格の大きな特徴は、比較的短期間で取得でき、現場での需要が非常に高いことです。
普通免許を取得していれば、おおよそ4日程度の講習で修了し、取得することができます。
さらに、物流業界や倉庫業など、他業種への転職にも強く、とても汎用性の高い資格です。
工場で長く働きたい人にとって、最初に取得しておくべき資格の一つといえるでしょう!
【フォークリフトの資格には、以下の2種類がある】
- フォークリフト運転技能講習:最大積載荷重量が1トン以上のフォークリフトを運転できる資格
- フォークリフトの運転の業務に関わる特別教育:最大積載荷重量が1トン未満のフォークリフトを運転できる資格
【フォークリフト運転技能者試験の概要】
| 受験資格 | 18歳以上 |
| 合格率 | 90%以上 |
| 難易度 | ★ |
| 講習内容 | フォークリフトの走行装置、荷役装置、力学、法令 |
| 参考URL | 各教習所による |
玉掛け技能講習
玉掛け技能講習は、クレーンで荷物を吊り上げる際にワイヤーロープやフックを正しく掛け外しするための国家資格です。
玉掛け作業は一見単純に見えますが、荷物の重量や形状、バランスを正確に判断し、安全に吊り上げる高度な知識と技術が求められます。
工場では、金型や製品・設備の移動でクレーンを使う機会が多く、この資格を持つことで安全に効率よく作業を進められる人材として評価されます。
講習自体は3日間で修了でき、初心者でも実践的なスキルを身につけられるのが特徴です。
また、建設現場等でも重量物を安全に扱うために必要とされ、多くの作業現場で重宝されます。
【玉掛け作業の資格には、以下の2種類がある】
- 玉掛け技能講習:吊り上げ荷重1トン以上の大型クレーンの玉掛け作業を行う
- 玉掛け特別教育:吊り上げ荷重1トン未満のクレーンの玉掛け作業を行うには資格は必要ないが、特別教育が望ましい
【玉掛け技能講習の概要】
| 受験資格 | 18歳以上 |
| 合格率 | 95%以上 |
| 難易度 | ★ |
| 講習内容 | 【学科試験】 ①クレーン等に関する知識(1時間) ②クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識(3時間) ③クレーン等の玉掛けの方法(7時間) ④関係法令(1時間) ⑤学科試験 【実技試験】 ①クレーン等の玉掛(6時間) ②クレーン等の運転のための合図(1時間) ③実技試験 |
| 参考URL | https://cranenet.or.jp/tisiki/tamagake.html |
クレーン運転士
クレーン運転士の資格は、クレーンを運転する際に必要となる国家資格です。
玉掛けとセットで取得する事が多く、大型機械や重量物を扱う現場では特に需要があります。
クレーンの資格には、2種類の免許と、技能講習・特別教育を受講する方法がありますが、
それぞれ運転できるクレーンの種類が異なりますので、職場の用途に合わせて選択しましょう。
【クレーン運転士の資格には、以下の種類がある】
- クレーン・デリック運転士免許:移動式クレーンを除き、吊り上げ荷重5トン以上のクレーンを運転できる
- 移動式クレーン運転士免許:吊り上げ荷重5トン以上の移動式クレーンを運転できる
- 技能講習: 5トン未満のクレーンや、1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンを運転できる
- 特別教育: 5トン未満のクレーンや、1トン未満の小型移動式クレーンを運転できる
【クレーン運転士の概要】
| 受験資格 | 18歳以上 |
| 合格率 | クレーン・デリック:60%(学科)、49%(実技) |
| 難易度 | ★★★ |
| 講習内容 | 【学科試験】 クレーンおよびデリックに関する知識 関係法令 原動機および電気に関する知識 クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 【実技試験】 クレーンの運転 クレーンの運転のための合図 |
| 参考URL | https://cranenet.or.jp/index.html |
QC検定(品質管理検定)
QC検定は、製品や工程の品質を管理・改善するための知識と実践力を評価する資格です。
工場では、生産の安定や不良品の削減などに直結するため、高い評価を受けます。
この検定では、「不良の防止」「工程の安定化」「データ分析」「問題解決」など、製造現場で必要とされる品質改善の考え方や手法を身につけられます。
QC検定を取得することで、製造現場の改善活動や品質保証業務において信頼を得やすくなります。
【QC検定の試験には、1〜4級まである】
- 1級は、品質管理の手法・実践問題に加え、テーマに沿った論述問題も出題される
- 2級は、「QC七つ道具」を駆使し、自らが中心となり、問題解決や改善ができるレベル
- 3級は、図、グラフ、散布図など「QC七つ道具」の理解、作り方、使い方の知識
- 4級は、品質管理の基本的な知識と理解を問うもの
| 受験資格 | 特になし |
| 合格率 | 1級:10%以下 準1級:10〜20% 2級:20%台~30% 3級:50%前後 4級:85%前後 |
| 難易度 | 1級:★★★★★ 準1級:★★★★★ 2級:★★★★★ 3級:★★★ 4級:★ |
| 講習内容 | 品質管理の実践 「QC的なものの見方・考え方」「品質の概念・管理方法」「品質保証」「品質経営」などの基本的な概念や言葉の定義。 品質管理の手法 特に「QC七つ道具」を中心に、各種データの基本的な扱い方。 |
| 参考URL | https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/qc/ |
危険物取扱者(乙種第4類)
危険物取扱者(乙種第4類)は、ガソリン・灯油・アルコールなど、引火性のある液体を安全に取り扱うための国家資格です。
製造業や化学工場、倉庫、ガソリンスタンドなど、多くの現場で重宝されます。
この資格を持つことで、危険物を「扱う」「保管する」「移動する」といった作業を法的に行えるようになります。
特に、塗料・溶剤・燃料などを扱う製造現場では、安全管理者やリーダー職に求められることが多く、安全意識の高さを示す指標にもなります。
試験では、危険物の性質、法令、安全管理の基礎知識が問われるため、学習を通して現場でのリスク判断力も身につきます。
【危険物取扱者の資格には、甲種・乙種・丙種の3種がある】
- 甲種:すべての種類の危険物
- 乙種:1類から6類までのいずれか。特定の種類の危険物のみ。
・1類: 酸化性固体
・2類: 可燃性固体
・3類: 自然発火性物質・禁水性物質
・4類: 引火性液体(ガソリン、アルコール類など)
・5類: 自己反応性物質
・6類: 酸化性液体 - 丙種:特定の危険物のみ
| 受験資格 | 乙種、丙種:特になし 甲種: ①化学系の大学を卒業している ②大学で化学系の授業科目を15単位以上取得いている ③乙種1類~6類のいずれかに合格し、実務経験が2年以上ある ④乙種1類か乙種6類、乙種2類or乙種4類、乙種3類、 乙種5類の4種類以上の交付を受けている ⑤ 修士・博士の学位を有する |
| 合格率 | 甲種:30% 乙種第4類: 30~40% 丙種:50%前後 |
| 難易度 | 甲:★★★★★ 乙:★★★★ 丙:★★ |
| 講習内容 | 危険物に関する法令 物理学及び化学 燃焼及び消火に関する基礎知識 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 |
| 参考URL | https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/ |
第二種電気工事士
第二種電気工事士は、工場内の電気設備や機械装置の配線・点検・修理を行うために必要な国家資格です。
電気に関する基礎知識と実務スキルを証明できるため、製造業の現場では非常に評価されやすい資格です。
この資格を持っていると、工場内のコンセントや照明、制御盤などの電気工事を自ら行えるようになり、設備の保守やトラブル対応の幅が広がります。
特に、自動化設備や生産ラインを扱う工場では、電気に関する知識が生産性の維持や故障対応に直結するため、現場で重宝されます。
試験は筆記と実技に分かれており、電気の基礎理論・配線図の読み取り・実際の結線作業などを学びます。資格取得によって、電気関係の部署や設備保全職へのキャリアチェンジもしやすくなり、転職のチャンスを広げることができます。
【電気工事士の資格には、第一種電気工事士・第二種電気工事士の2種がある】
- 第一種電気工事士(500キロワット未満の自家用電気工作物の工事)
- 第二種電気工事士(600ボルト以下の一般用電気工作物の工事)
| 受験資格 | 特になし |
| 合格率 | 第一種電気工事士:60%前後 第二種電気工事士:70%前後 |
| 難易度 | 第一種電気工事士:★★★ 第二種電気工事士:★★★ |
| 講習内容 | ・電気に関する基礎理論 ・配電理論および配線設計 ・電気応用 【筆記試験】 ・電気機器・蓄電池・配線器具・電気工事用の材料および工具ならびに受電設備 ・電気工事の施工方法 ・自家用電気工作物の検査方法 ・配線図 ・発電施設・送電施設および変電施設の基礎的な構造および特性 ・一般用電気工作物および自家用電気工作物の保安に関する法令 【技能試験】 ・電線の接続 ・配線工事 ・電気機器・蓄電池および配線器具の設置 ・電気機器・蓄電池・配線器具ならびに電気工事用の材料および工具の使用方法 ・コードおよびキャブタイヤケーブルの取り付け ・接地工事 ・電流・電圧・電力および電気抵抗の測定 ・自家用電気工作物の検査 ・自家用電気工作物の操作および故障箇所の修理 |
| 参考URL | https://www.shiken.or.jp/ |
機械保全技能士
機械保全技能士は、機械や設備の点検・修理・保全に関する技能を証明する国家資格です。
生産ラインの安定稼働を支える重要な役割を担い、トラブルを未然に防ぐスキルが身につきます。
資格区分は1級から3級まであり、経験やスキルに応じてステップアップできます。
試験では、機械の構造や作動原理、摩耗・故障の原因分析、保全計画の立て方などを学び、実技では実際のトラブル対応力も問われます。
結果として、生産効率の向上や設備の寿命延長につながり、保全職や生産技術職などへのキャリアアップにも有利です。
【機械保全技能士の資格には、特級、1級、2級、3級の4種がある】
- 特級:対象目安は、保全部門の管理職。保全業務の監督者として、リソースの割り振りや評価などのマネジメント業務に携わる。
- 1級:対象目安は、部門や保全部門のリーダー格として、チームのメンバーを指導・育成する。
- 2級:対象目安は、新入社員から中堅社員。保全作業員やオペレーターとして、基本的な知識やスキルを活かす。
- 3級:対象目安は、学生や新入社員。機械保全の初級レベルの知識やスキルを習得する。
| 受験資格 | 特級:1級合格後、実務経験5年以上 1級:実務経験7年以上。2級合格者は実務経験2年以上、 3級合格者は実務経験4年以上で受験可能。 2級:実務経験2年以上。3級合格者は実務経験なしで受験可能。 3級:実務経験不問(年齢、学歴を問わず誰でも受験可能)。 |
| 合格率 | 特級:20%前後 1級:30%前後 2級:35%前後 3級:75%前後 |
| 難易度 | 特級:★★★★★ 1級:★★★★★ 2級:★★★★★ 3級:★★ |
| 講習内容 | 特級:工程管理・作業管理・品質管理・原価管理・安全衛生管理・作業指導・設備管理 1級:機械系保全作業・電気保全作業・設備診断作業のうちいずれかひとつ 2級:機械系保全作業・電気保全作業・設備診断作業のうちいずれかひとつ 3級:機械系保全作業・電気系保全作業のうちいずれかひとつ |
| 参考URL | https://www.shiken.or.jp/ |
衛生管理者
衛生管理者は、労働者の健康と安全を守るために職場環境を管理する国家資格です。
常時50人以上の従業員がいる事業所では必ず選任が義務づけられている重要な資格です。
工場では、作業環境に粉じん・騒音・化学物質などのリスクがあるため、特に重宝されます。
資格は「第一種」と「第二種」に分かれており、試験では、労働衛生・関係法令・作業管理・健康管理などを学び、職場環境の改善や従業員の健康管理に関する専門知識が身につきます。
この資格を取得すると、工場内の安全衛生体制の中心的役割を担えるようになり、安全意識の高い職場づくりや事故防止に貢献できるのが大きな特徴です。
【衛生管理者の資格には、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者免許の2種がある】
- 第一種衛生管理者免許:すべての業種の事業場において衛生管理者となることができる。
- 第二種衛生管理者免許:有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の衛生管理者となることができる。
| 受験資格 | 第一種衛生管理者、第二種衛生管理者も共通 ・大学や高等専門学校を卒業した者で、 1年以上の労働衛生の実務に従事したことがあること ・省庁大学校を卒業した者で、 1年以上の労働衛生の実務に従事したことがあること ・高等学校や中高一貫校を卒業した者で、 3年以上の労働衛生の実務に従事したことがあること ・10年以上の労働衛生の実務に従事した経験がある者 |
| 合格率 | 第一種:45~50% 第二種:50~60% |
| 難易度 | 第一種:★★★ 第二種:★★★ |
| 講習内容 | 第一種衛生管理者:関係法令、労働衛生、労働生理 第二種衛生管理者:上記から有害業務にかかるものを除いたもの |
| 参考URL | https://www.exam.or.jp/introduction/h_shokai502/ |
工場勤務で資格を取得する際の注意点3つ
取得することを目的にしない
資格取得を目的にしてしまうと、本来の「仕事に活かす」という目的からズレてしまいます。
資格はあくまでスキルを証明する手段であり、取得そのものがゴールではありません。
重要なのは、今の仕事や将来のキャリアに役立つ資格を選び、学んだ内容を実務に活かしていくことです。
その知識・経験を現場で使ってこそ価値が高まります。
難易度を確認してから挑戦をする
必要な勉強量や試験内容を把握していないと、途中で挫折しやすくなります。
繁忙期には、学習時間が限られることが多く、難易度の高い資格にいきなり挑むと仕事との両立が難しくなる可能性があります。
また、資格によっては専門知識や実務経験が必要な場合もあり、準備不足のまま受験しても合格が難しいことがあります。
事前に、試験の難易度と必要学習時間を理解しておくことで、計画的な学習計画が立てられ、効率よく合格を目指すことができるでしょう。
実技試験がある場合が多い
工場で取得する資格に実技試験が多いのは、現場で即戦力として安全かつ正確に作業できるかを確認する必要があるためです。
工場の仕事は、フォークリフトの運転、玉掛け作業、溶接、電気工事など、実際の操作スキルがそのまま作業品質や安全に直結します。
知識だけでは安全に作業できないため、実技試験を通じて「正しい手順で作業できるか」「危険を回避する操作が身についているか」「現場で求められる精度を満たしているか」を評価します。
そのため、資格取得を目指す際は、学科試験だけでなく実技対策にも時間が必要であり、講習や練習環境を確保しなければならない点に注意が必要です。
まとめ|自分に合った資格で工場勤務をもっと有利に

自分の職種・将来像に合わせた資格選びが重要
資格取得で最も大切なのは、自分の職種や将来なりたい姿に合った資格を選ぶことです。
なぜなら、資格は「持っているだけで意味があるもの」ではなく、「実際のキャリアで活かしてこそ価値が出るもの」だからです。
自分の仕事内容や今後挑戦したいポジションに合った資格を選ぶことで、日々の業務の理解が深まり、評価にも反映されやすくなります。
また、将来の転職やキャリアアップでも「必要なスキルを持っている人」として高く評価されるため、資格がより効果的に活かせます。
つまり、「何となく取る資格」ではなく「目的に直結する資格」を選ぶことが、工場勤務で資格を最大限に活用するための鍵となります。


